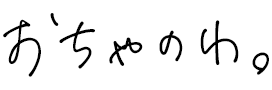夏の夜、茶室に灯る竹の光。白白庵の恒例企画となった「夏の宵茶会」が、2019年も開催されました。
埼玉県東松山市を中心に活動する造形家・加藤渉が、3年連続となるこの茶会に参加。今回は錆竹を用いた掛け花入れ「鵲」が、展覧会のパンフレットを飾りました。竹という素材の可能性を追求し続ける造形家・加藤渉の新たな挑戦です。
目次
錆竹が生み出す静謐な美「鵲」
- 作品名:鵲(かささぎ)
- 製作年:2019年
- 素材:真竹(錆竹)、クルミ、真鍮、アクリル、LED、他
「鵲」は、経年変化によって独特の色合いを帯びた錆竹を主材料とした掛け花入れです。竹の節を巧みに活かした舟形の造形に、クルミ材と真鍮、そしてLEDを組み合わせることで、伝統と現代技術が見事に調和しています。

作品名である「鵲(かささぎ)」は、七夕伝説で織姫と彦星の橋渡しをする鳥として知られています。光を放つこの花入れもまた、過去と未来、伝統と革新を繋ぐ存在として、茶室空間に静かな物語を紡ぎます。
内部に仕込まれたLEDの光が、錆竹特有の渋い色調を透かし、生けられた一枝を優しく照らし出す様は、夏の夜の茶事にふさわしい風情を醸し出しています。
イベント概要
白白庵 特別企画 | Night Gallery 2019「夏の宵茶会」
- 会期:2019年7月6日(土)~17日(水) ※木曜定休
- 時間:11:00~21:00(ナイトギャラリー営業により通常より1時間延長)
- 会場:白白庵(ぱくぱくあん)
メイン会場:3階ギャラリー、1階茶室と2階カウンターを連動
〒106-0072 東京都港区南青山二丁目17-14
造形家・加藤渉と白白庵での活動
埼玉県東松山市を拠点に活動する造形家・加藤渉氏にとって、白白庵での「夏の宵茶会」は重要な発表の場となっています。2018年の「Infinity」に続き、2019年は「鵲」を出展。竹という一貫した素材を用いながらも、毎年異なる表現で茶の湯空間に新しい息吹を吹き込んでいます。
造形家・加藤渉氏の作品は、単なる茶道具を超えて、光と影、静と動、伝統と革新が交差する空間芸術として評価されています。白白庵という茶の湯文化の最前線で、継続的に作品を発表し続けることで、現代における茶道具の可能性を切り拓いています。
造形家・加藤渉、ものづくりの系譜

経歴
1985年、埼玉県比企郡鳩山町生まれ。Webデザイナー・プログラマーを経て、2007年頃より竹や和紙を使った照明造形の世界へ。パルプ造形家の故・大川修作氏に師事し、ものづくりの本質を学びました。
現在は東松山市を中心に活動する造形家として、木竹・和紙・ガラス・石材・金属など多様な素材を自在に操り、照明作品や造形作品を制作しています。特に竹を用いた作品では、素材の持つ自然な美しさを活かしながら、現代的な感性を融合させた独自の表現を確立しています。
茶の湯空間での活動
東松山市を中心に活動する造形家・加藤渉氏は、白白庵での継続的な出展をはじめ、増上寺での「陰翳礼讃」展、新宿伊勢丹での茶会など、茶の湯文化に深く関わる活動を展開。光と影を巧みに操る造形家として、夜の茶事「夜咄」の世界に新しい解釈をもたらしています。
主な実績
造形家・加藤渉の作品は、東京国立博物館での国際文化交流イベントの空間演出や、東松山市近郊の埼玉県内での地域文化活動にも活用され、幅広い分野で評価されています。
- 2019年7月 Night Gallery 2019「夏の宵茶会」白白庵(本展)
- 2019年3月「南青山大茶湯」白白庵リニューアル企画
- 2018年7月「夏の宵茶会」白白庵
- 2018年1月 東京国立博物館「アラビアの道」レセプション空間演出
- 2017年12月「竹あかりと初詣コンサート」ときがわ町桃木八幡神社
- 2016年7月「新・陰翳礼讃」白白庵
- 2016年7月 二人展「続・陰翳礼讃」増上寺
おちゃのわでは、お茶文化を支える作家たちの活動をご紹介しています。伝統と現代が交わる場所で、新しい茶の湯の表現を探求する作家たちの挑戦を、これからもお伝えしていきます。